記事内に商品プロモーションを含む場合があります
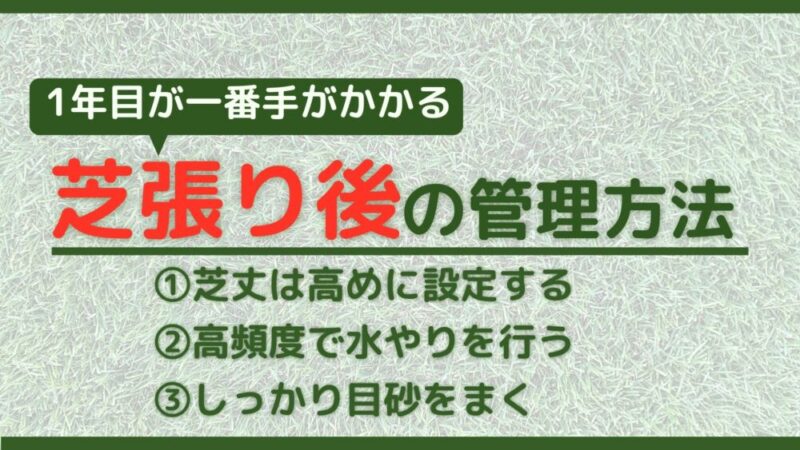

- 水やりってどれくらいすればいいの?
- いつになったら芝刈りをしたらいいの?
- 全然、密にならないんだけど…。
- むしろ、なんか枯れてきた。
芝張り直後って不安なことも多く、管理不足で枯らしてしまうトラブルも多い時期です。初心者の方に多い失敗例と適切な管理方法をまとめてみました。
1年目の芝生管理で気をつけてほしいポイントは以下の通りです。
- 目土はたっぷりと
- 水やりは小まめに
- 芝刈りは少し長めに
- 肥料はしなくて大丈夫
これから詳しく説明していきますね。
目土編|葉先がちょんと出る程度まで被せる

芝張りの際、再度の仕上げに芝生の上や目地に目土を入れます。意外と多いのが、この目土が不足しているケース。
芝張り時における目土の役割は以下の3つです。
- 乾燥を防ぐ
- 新芽の成長を促す
- 凸凹をならす
乾燥を防ぐ
芝生の根が地表にむき出しになっていると、水分を吸収できません。
目土を被せることによって、目土が水分を保持してくれるので地表部分の乾燥を防いでくれます。
その結果、根から水分を吸収しやすい環境に整えられます。
新芽の成長を促す
目土のもう一つの役割として新芽の成長を促す効果があります。
芝生の密度を上げるためには、茎が横に広がる匍匐茎(ほふくけい)を伸ばす必要があります。
匍匐茎は、基本的には土のあるところにしか伸びていきません。張ったばかりの芝生と芝生の間に溝があると、成長しにくい環境になってしまいます。
凸凹をならす
目土によって、凸凹をならすことも芝生管理においてとても重要です。
凸凹があると、芝刈りを押しにくくなったり、肥料焼けや病害が発生しやすくなったりします。
なぜ、肥料焼けや病害が発生しやすくなるかというと、凹んでいる部分に水たまりができてしまうからです。
まいた肥料が高いところから低いところに流れてしまい、肥料成分が局所に集中することによって、肥料焼けを起こします。
また、水たまりを媒介として病原菌が繁殖し、病害が発生するリスクも高まります。
目土が少なくなっていることに気づいたらその都度、目土を追加するようにしましょう。
目土の目安は葉先が少し飛び出す程度です。完全に芝生が埋まってしまうと光合成ができなくなってしまい、弱らせてしまうので埋めすぎには注意してください。
水やり編|はじめは毎日。夏場はとくに水切れに注意。

芝張り直後、一番重要になってくるのが水やりです。張ったばかりの芝生の根は短く、水を吸い上げる力が非常に弱いので、水切れに要注意。
芝生を張ってからの時期に応じて散水頻度を調整する必要があるので詳しく解説します。
芝張り直後の3週間はほぼ毎日水やりが必要
芝張り直後の芝生の根は短いため、毎日、水やりをする必要があります。可能であれば、芝張り直後の1~2週間は、朝と夕方の1日2回の水やりが望ましいです。
水やりをする前は、「水切れサイン」が出ていないか毎回チェックすることをおすすめします。
水切れサインとは、芝生が水不足になったときに起きる症状の一つで、葉が丸くなり、針のように尖った形状になることを言います。
芝張りから4週目以降は徐々に水やりの頻度を減らしても大丈夫
芝生を張ってから4週間ほど経過したら、たまに芝生を引っ張って、根の張り具合を確認しましょう。
引っ張っても芝生が浮いてこなくなったら、徐々に散水頻度を少なくしても大丈夫です。
むしろ、水やりの間隔を少し空けることで、地表部分の過剰な湿度を抑制できるので、病害対策にもつながります。
- 根の張り具合のチェック方法
- 根が張っていない芝生は、引っ張ることで浮き上がってしまいます。
一方、根が張っている芝生は引っ張っても浮き上がることはありません。
ただし、夏場は気温が高く、水切れを起こしやすいので、芝生1年目の夏場は毎日水やりを行うことをおすすめします。
なお、水やりをする際は、気温の高い時間帯は避け、早朝か夕方が適しています。
なぜなら、気温が高い時間帯に水やりをしてしまうと、地表部がサウナ状態になり、芝生にダメージを与えてしまうからです。
「毎日の水やりが大変」「そんな時間がないよ」という方にはスプリンクラーがおすすめです。
なかでも、「ガルデナアクアズーム」は、スプリンクラーの中でも使い勝手がよく、どんなお庭にもマッチしてくれます。
ガルデナアクアズームのレビュー記事も書いていますので、気になる方はチェックしてください。
また、ホースリールをまだ購入されていない人は、あらかじめホースの内径が太いものを選ぶことをオススメします。
その理由は、ホースの内径が狭いものだと流水量が少なく、水やりにかかる時間が長くなってしまうからです。
下記におすすめのホースリールを紹介しておきます。
芝刈り編|初年度は芝丈を長めに管理する。

芝刈りいつからやればいいの問題。初心者あるあるだと思います。
芝張り後、最初の芝刈りは3~6週間後、芝生を引っ張ってしっかり根付いていることを確認できれば芝刈りしても大丈夫です。
ただ、芝刈りを行う上で重要なことは、芝生を必要以上に短くしないということ。張りたての芝生はまだ根が浅く脆弱です。芝張り初年度は根を深く張れるように葉は長めに管理してあげましょう。
具体的には、25mm以上が芝刈り頻度も少なく済むので初心者にはおすすめです。短めの管理や密度を上げるのは2年目以降にチャレンジした方がトラブルが少なく済みます。
秋以降は30㎜以上で管理しましょう。葉を長くすることで、根への栄養を備蓄する効果が期待できます。来春の芽吹きにに左右するので、必ず押さえておきたいポイントです。
芝刈り機で一番人気は、キンボシの「ハッピーバーディーモアー」です。
コンパクトサイズで女性でも使いやすい軽量化された手動芝刈り機です。
ホームセンターで研磨の無料サービスが定期的に実施されており、メンテナンスしやすい点も魅力です。
肥料編|根が成長していないうちは不要。

根が十分に生育するまでは不要です。根が短いと十分に養分を吸収することができないので、周囲の雑草に養分が取られてしまいます。
そもそも、芝張り時に元肥として肥料を混ぜているはずなので、追加で肥料をまいてしまうと、栄養過多になり、病気になるリスクが高まります。
芝生1年目は、あわてず根が張るのをゆっくりと待ちましょう。
ちなみに、どうしても肥料をまきたいという人は、芝生の成長が遅くなる秋に1度だけ行いましょう。来春の芽吹きに向けた栄養になります。
秋・冬に芝張りする際の注意点
休眠中の芝生で張った際、中には質の悪い芝生が混じっていることもあります。
残念ながらその芝生は枯れてしまうリスクが高く、撤去して新しい芝生と入れ替えるか、目土を追加して周囲の芝生が伸びてくるのを待つしかありません。
芝生選びで失敗したくない方は、休眠あけの少し芽吹き始めた芝生を選ぶようにしましょう。時期的には3~5月がおすすめです。
まとめ
この記事のまとめ
- 適宜、目土を追加する。目安は葉先が飛び出す程度。
- 水やりは張った直後や夏場はほぼ毎日。根が張ってから徐々に間隔をあける。
- 芝刈りは、根が張ったことを確認したから。少し長めに管理するのがベスト。
- 肥料は基本的に不要。やるなら秋ころに1回で十分
